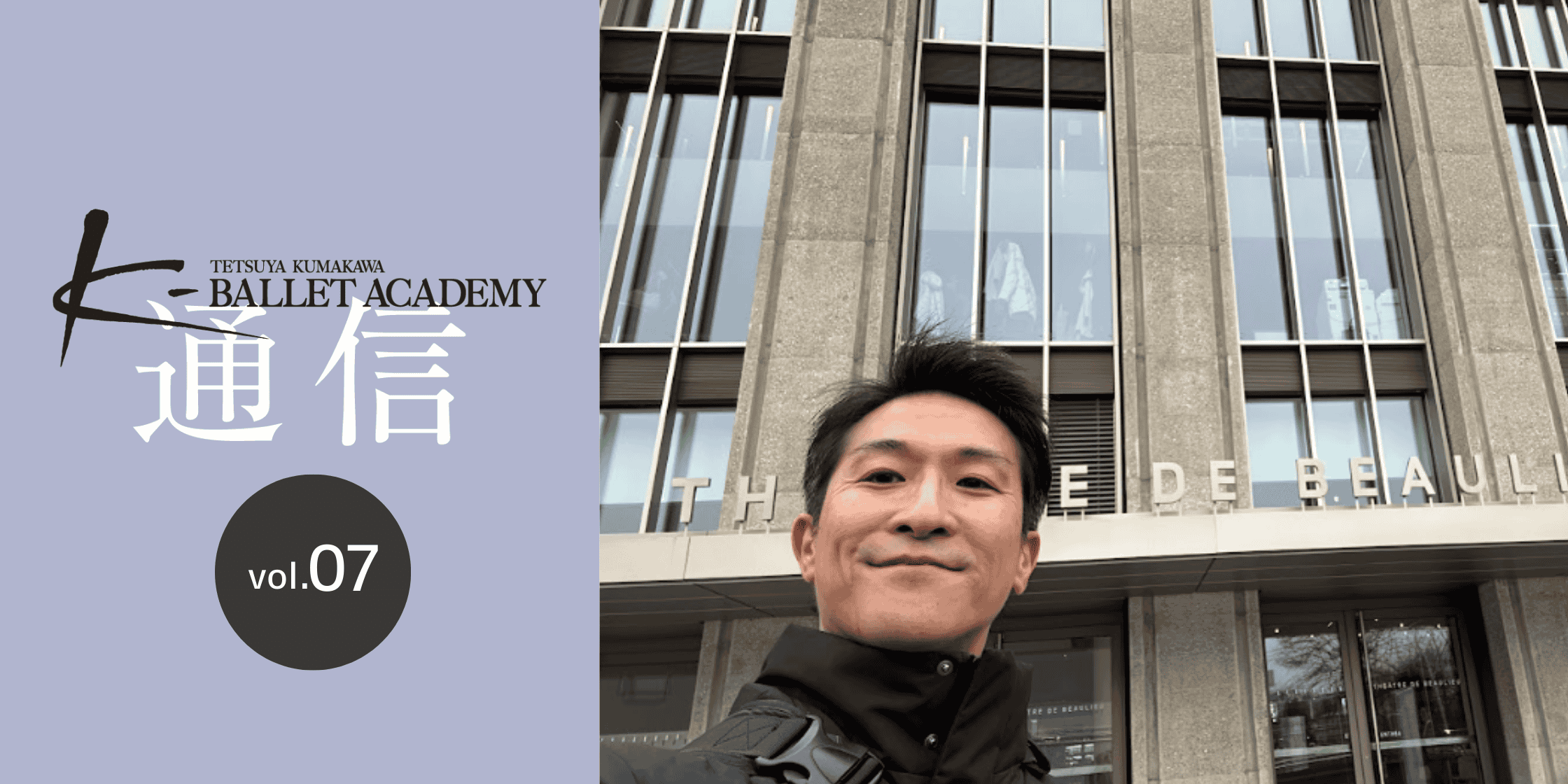今年も2月にローザンヌ国際バレエコンクールが開催されました。Kバレエ トウキョウはコンクールのパートナーカンパニーですので、私も視察のためにローザンヌに出向き、パートナーカンパニー向けに開催されるさまざまなイベントへ参加しました。
前回の「アカデミー通信」で書きましたが、私がコンクールに参加した際はモスクワのボリショイ劇場での開催でしたので、今回初めて本拠地ボーリュ劇場を訪れることができました。

同コンクールでスカラーシップをいただき英国ロイヤル・バレエ学校に留学ができたわけで、それがなければ熊川ディレクターとの出会いもありませんし、今こうしてKバレエにいることもないと思いますので、このコンクールは私にとっては特別なものです。
期間中は世界中から集まった芸術監督や校長先生方とのたくさんの刺激ある交流がありましたが、なかでもパートナーカンパニーとスクールが出席して行われる「ネットワーキング・ミーティング」は大変興味深いものでした。トピックスは若手のダンサー育成について、コンクールの存在・参加意義について、各バレエカンパニーのオーディションの現状について、男性振付家の減少について、優秀なダンサーの発掘への課題について、バレエを習う子供たちの人数の減少について、若手ダンサーのカンパニー早期脱退についてなどです。参加者が各々の国で抱えている問題意識を話し、積極的に意見を交わし合う場でした。特にコンクールの参加意義、また存在意義については、各国の方々からもさまざまな意見がありましたが、私としてはコンクールはダンサーを成長させるための素晴らしい場所だと思っています。審査員や同じ情熱を持つ仲間から貴重な知識と見識を得ることができ、肉体的にも精神的にも成長する機会を与えてくれるからです。しかしもちろん、コンクールだけで芸術性や可能性のすべては測れませんから、参加する生徒にも、これがダンサーとしての将来を決める最終決定の場所ではないこと、参加する意味を履き違えないようにとは話しています。

また、ミーティングの議題ではありませんでしたが、リアルタイムのトピックスとして各国の皆さんとの会話の中で、頻繁に話題に出たのは、ダンサーの体型の改善について指導者とダンサーが今後どうコミュニケーションを取っていくかということでした。皆さんの話を総合すると、特にヨーロッパやアメリカの国々では、ダンサーの体型に関して、指導者から直接ダンサーに体型を改善するよう求めることが年々難しくなっているとのこと。痩せすぎているダンサーに食事指導や、もっと食べたほうが良いと話すのは特に問題はないですが、ウェイトオーバーの生徒に痩せたほうがいいというのはとてもセンシティヴであり、以前よりダイレクトに伝えることが難しいということでした。しかし難しいのは、その結果はプロになるためのオーディションではシビアな結果につながることです。結局プロのダンサーとして雇用されるには、体型はとても重要視される要素なのですから。
ローザンヌ国際バレエコンクール後に、ドイツで開催されたYGPジョブフェア(国際的なバレエ団合同オーディション)にもお招きいただいたのですが、各国の芸術監督の皆さんとの間でも同じような話が出ました。技術的に問題ないダンサーでも体型が理由で、契約をあげられない方が多くなっていること。オファーできない理由が体型だけであるダンサーに、「体型を改善できるのならコントラクトを考えてもよい」という話をすることが難しい今は、それができないことを皆さんとても複雑な思いで話していました。必要以上に子供を傷つけることはもちろん避けるべきことですが、「プロを目指す(=バレエ団の契約を取ること)」を目標として日夜すべてをかけてバレエに励む生徒たちに、もしその目標達成を妨げる要素が現在の(変えることができる)体型なのであれば、それを伝えることはバレエ教師の義務でもあることを改めて実感することとなりました。


最後に余談ではありますが、私が冒頭で、今Kバレエにいるのもこのコンクールのおかげだと言ったのは理由があります。2年前、熊川ディレクターはローザンヌ国際バレエコンクールの審査員を務めましたが、コンクール後に熊川ディレクターがロンドンに立ち寄ることになったのです。そこで「時間があるなら会おう」と連絡をいただき、ロンドンで再会し、Kバレエへ来ないかとのお誘いがあったのです。ですから、熊川ディレクターがローザンヌに行かなければ、私は今こうしてKバレエにいることはなかったかもしれないのです(笑)。